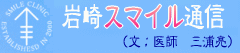
2011年1月号 2ページ目
① 一卵性双生児の諸研究によると、才能の70%以上は遺伝であると考えられる。
その後の親の子育てはほとんど子供の能力に関係がないことも合わせて分かっている。
つまり向いていることは、やればカナリできるようになるが、むいていないことは頑張ったとしてもせいぜいソコソコどまり。
② かならず人には、子供の頃から
「なぜか得意」
なことがある。
それは人によってまちまち。
また、能力には種類がいろいろある。
③ 能力主義は道徳的にも正しい。
能力主義でないと、人種、国籍、性別、宗教、思想、容姿、家柄が基準になることは歴史が証明しているから。
また、時代が能力主義を重視する傾向は良くも悪くも誰にも止められない。
発展途上国の優秀な人が先進国のソコソコの能力の人の待遇をどんどん追い越しはじめている。
発展途上国の人が3人幸福になると、一人の先進国の人が不幸になるかもしれないが人類全体では幸福になっている。
④ 多くの仕事はマクドナルド化がすすみ、誰でもできるようになる。
そのような仕事の賃金は下がる。
しかし、創造性がもとめられる仕事はそうはならない。
⑤ 人は笑ったり泣いたりしてから、その理由を後付で考えている。
つまり、無意識の方が意識できることより比重が高い。
だから人はそんなカンタンに性格をかえることなんてできない。
⑥ 狭く濃い人間関係より、浅く広い人間関係の方が広がってきている。
そこには家族、友情といった感情をともなうエコひいき中心の関係はない。
自分が相手に対し価値有る何かを先ず差し出すことで、評判の輪が広がってゆくサイクルが続く。
他人に利益を与え信頼を得ることで自分の価値をドンドン上げてゆくことができ、今まで閉鎖空間であった家庭、学校などではうまくやれずにはみ出し気味であった人でも、何らかの才能があればつぶされることはなく、生きやすくなってゆく。
そこにはいじめ、服従、強制といった古来の価値観はない。
⑦ 昔は権力者が世の中を牛耳っていた。
それは政治的な権力ゲームであり、相手を服従させるゲームであった。
今は服従させるより、相手に利益を与え、評判を得るゲームの勝者の方が上。
昔は権力社会の犠牲者が確かにいた。
今の時代には犠牲者はいない。
ただ評判社会のゲームに適応できず、愛情、友情空間にしか適応できない人はいる。
20世紀少年という映画では、ともだちが唯一の価値観であり、それを相手に強制、受け入れられないと絶交(=殺害)する醜悪なカルト宗教が描かれていた。
⑧ 自分の子供の頃からの得意分野をよく考え、そこを伸ばすべき。
ただし工夫は必要。
工夫して狭い範囲でいいから、自分の得意なことで、かつ勝算のあるルールを自分でつくりだす。
そこで評判を得て生き残ればいい。
評判をめぐるゲームに序列はない。
モナコの社交界の評判獲得ゲームには選ばれた大富豪にしか参加資格がないが、ゲームはそれだけではなく無数にある。