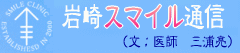
2011年5月号 3ページ目
⑥ 解決結果;ある人;ある一定の幅はあるものの、それなりの結果に収束。
ない人;スゴクうまくいくときと、全くうまくいかないときの落差が激しい。
⑦ フツーか、特別か?;ある人;今回の問題もそう特殊ではないと冷静。
自分は能力、環境ともフツーの人間だと考える。
ない人;今回はレアケースであり、特殊だと思い込む。
自分が置かれた環境が良くも悪くも特殊だと考えている。
経験至上主義。
物事の共通点を探すことや、一般化がキライ。
⑧ はじめか、おわりか?ある人;結論から考える、ない人;はじめから考える。
⑨ 責任;ある人;さっさと自分が結果に対して責任を負う;ない人;誰が責任を負うかどうか?皆が自分を悪く思っていないかどうかを常に気にしている。
いかがでしたか。
結局、僕らが生活している中で、事前に完全な情報を得ることは出来ませんし、また割ける時間は常に限られていますから、このような地頭力がある方が生きやすいと思います。
このような事は意識しているかどうかだけで大分違うでしょうし、④みたいなことは、一旦紙にカンタンに書きだしてみて全体を眺めてからスタートすれば随分うまくやれるように思います。
⑤は長い期間の後で「ある人」はドンドン、解決レベルを上げてゆけますが、「ない人」は毎回結果に一喜一憂するだけで、同じ失敗を繰り返しそうです。
⑦では、フツーに冷静に対処することが重要のようです。
そういえばスゴイ人は大抵、自分はフツーだ、今回出会った問題もフツーの範囲だと思っています。
イマイチの人は自分が特殊に運が悪いとオオゲサで、自分って変わってる人だ、今回出会った問題は初めて出会ったタイプだ、特殊だ、と何でも特別だと思いがちのような気がします。
自分の視点だけでなく、時には自分を含んだ世界を、客観的に空から見下ろせるか?という点が重要のようです。
⑧では手段から考えるのではなく、目的から考える(例;ドリルをホームセンターに買いに来た人はドリルが欲しいのではなくて、壁に穴を開ける必要性、または壁に何かをかけられるようにしたいだけ。
目的が達せられるのであれば方法はドリルにこだわる必要は別にない)、「できること」でなく「やるべき事」を考える(例;電化製品を買うときに事前にどんな機能があれば自分のやりたい事が便利かを事前に考えている。
電気屋さんで、店員さんオススメのあれもできる、これもできるという高性能な物は本当に自分にとって必要な機能でなければお金のムダになる)、「自分」からでなく、「相手」から考える(例;人に伝達したいことがある場合、自分はちゃんと言いましたよ!と言い張るのか、それとも、何がどんだけ伝わったのか?何が伝わらなかったのか?を意識できたのかどうか。
ハナシが長いなーと思われるのか、この人の言う事は分かりやすいなーと思われるのか?も含まれます。
また情報はあれば良いでしょうが、それだけではゼンゼン解決は得られないということのようです。
もちろん、物知りタイプの知識力、機転を利かせて場の雰囲気が読めて対人感性力が高いこともそれなりに大事ですが、それだけでは個人の私が、今日、そして今からどうするのかにはなんの決断も下せません。
誰の人生でも日々、無数の選択肢から決断し行動した集大成で出来ています。
「個人の時代」を生きてゆくのに最後は地頭力を意識しているかどうかがものを言うような気がします(^^)